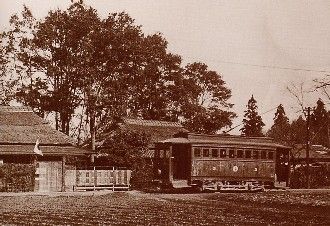水判土観音(戦国時代 岩槻の太田氏の陣屋になっていたため北条勢の襲撃をうけ 消失。江戸時代になって川越中院の末として寺領10石の朱印状を与えられ、再興される、ここには八百比丘尼伝説の碑もある。)
東照宮(西光院から移されたのかな?) 足立神社(北足立郡との名前との・・1912年植水地区20社が合祀)の日清戦争出征兵士の慰霊碑 馬宮の氷川神社(神社が二つ並んで 二つ宮) 土屋 金山神社(かなさん神社?)船渡橋の渡船場『昼間の渡し』 現在自動車教習場 (旧16号線 上江橋 あたりの 渡し舟の資料を求めます。)
昼間山西光院(東照宮 昼間修二氏所蔵の東照宮の扉)(天正年間 徳川家康が川越から岩槻へ向かう途中荒川を 夜 渡ったときの名主様が 篝火(かがりび)を炊いて足元を照らし 昼間の様な明るさに心を動かし 昼間 の姓を賜わり 渡し舟も「昼間の渡し」と命名されております)村人は渡し場付近に東照宮、権現堂を祀り家康公の徳を偲んだといいます 今は無き境内には家康が休息のため腰掛けた老松「御腰掛の松」があったといいます。
清河寺 大ケヤキ(落雷が原因で今では全容は見えません 代々鎌倉公方 足利氏の崇敬をうける 瓦 の家紋等 太田氏の文献も数多く所有 現在 県の文書館に寄託とのこと まだあるかな)また清河寺を水源とする 滝沼川 指扇中学校あたりで 今でも 大雨による冠水 で 道路が見えなくなってしまいます。 琵琶島氷川神社(赤羽根)6月にはアジサイ祭り
その真ん前に小さな山がありその頂に祠(ほこら)があります、荒沢不動石仏(奥州出羽山 梵字不動尊)では地域の12名ほどで講 を結んでいます。
花の丘公園の東 聖学院大学から東へ500m市境を流れる鴨川の斜面の上 三貫清水 太田道灌の井戸